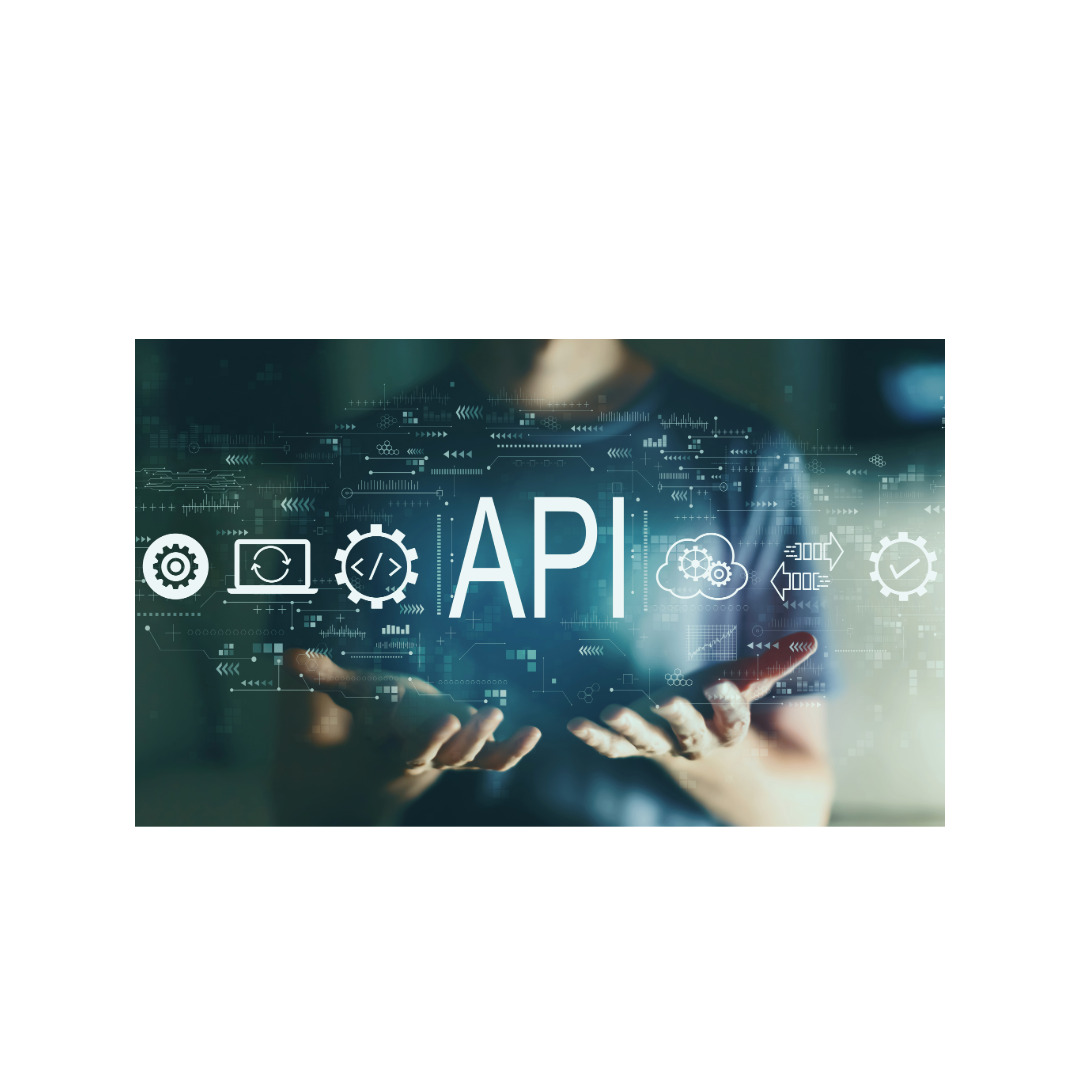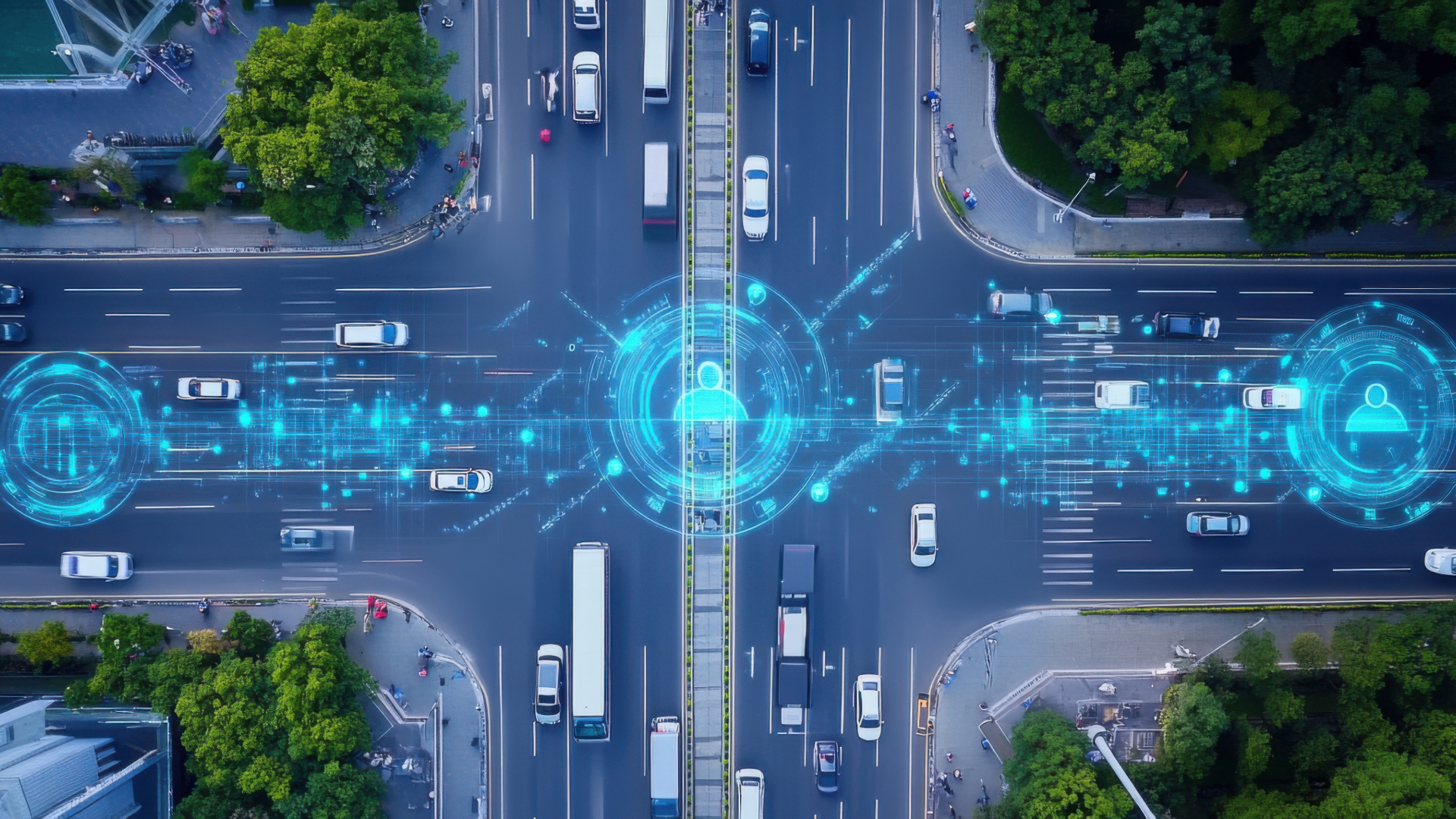はじめに
近年、各自治体が市民サービス向上のためにスマートフォンアプリを続々とリリースしています。ゴミ収集日のお知らせや防災情報、観光案内など多岐にわたる機能を提供する行政アプリ。
しかし、モビリティの重要な選択肢である自転車に関する機能が十分に組み込まれていないのが現状です。
持続可能な都市づくりが叫ばれる中、なぜ行政アプリは自転車の活用を促進する仕組みを積極的に取り入れないのでしょうか
要約
- 行政アプリの現状:
多くの自治体がスマートフォンアプリをリリースしているが、自転車関連機能の実装は限定的。
市民サービスとしての「自転車モビリティの位置づけが不明確」であり、アプリ開発時の「優先順位が低い」状況にある - 自転車関連データの不足:
自転車道や駐輪場などの「インフラ情報がデジタル化されておらず」、アプリに組み込むためのデータ基盤が整っていない。
自治体の縦割り行政により、「道路管理部門と交通政策部門の連携不足」も課題となっている - ニーズ把握の欠如:
自転車利用者の声が行政に届きにくく、どのような機能が求められているのかの把握が不十分。
「民間の自転車関連アプリとの差別化ポイントも不明確」で、公共サービスとしての独自価値の創出ができていない - 技術的課題と予算制約:
「自転車ルート最適化」や「安全情報提供」など高度な機能実装には技術的ハードルがあり、限られた予算内での開発優先順位が低くなりがち。自治体のデジタル人材不足も影響している
行政アプリに自転車機能が不足する背景
行政アプリの多くは、市民生活の基本サービス(ゴミ収集、防災、税金など)を中心に設計されており、モビリティ全般、特に自転車に関する機能は後回しになりがちです。
その背景には、自転車が「趣味」や「個人の交通手段」と位置づけられ、公共交通と比較して行政サービスの対象として「優先度が低く見られている」ことがあります。
また、日本の行政における自転車政策は、「道路交通法上の取り締まり対象」という側面が強調され、積極的な活用促進よりも管理や規制の文脈で語られることが多いという事情もあります。多くの自治体では自転車活用推進計画を策定していますが、それを「デジタルサービス」として展開する発想までは至っていないのが現状です
自転車業界への示唆
1. 行政との協働モデルの構築
自転車業界は、自治体のアプリ開発チームと積極的に連携し「業界が持つデータや知見を提供」すべきです。
例えば、販売店マップや修理スポット情報、安全な自転車ルートのデータなど、業界だからこそ持っている「情報をオープンデータ」として公開することで、行政アプリへの組み込みを促進できます。
また、自転車メーカーやショップが共同で、自治体へのデータ提供フォーマットを標準化することで、各地域の「アプリ開発コストを下げる取り組み」も有効でしょう
2. 利用者ニーズの可視化と提案
自転車業界は顧客との直接的な接点を持つ強みを活かし、利用者がどのような機能を行政アプリに求めているのかを「調査・分析」することが重要です。
例えば、販売店での購入時や修理時のアンケート、業界団体によるユーザー調査などを通じて具体的なニーズを収集し、それを行政に提案する役割を担うべきです。
「こういう機能があれば自転車利用者はもっと便利に、安全に走行できる」という具体的な提案は、行政側の理解を促進します。
3. 独自アプリとの連携API開発
民間の自転車関連アプリと「行政アプリをつなぐAPIの開発」を業界から提案することも一案です。
すでに存在する自転車ナビゲーションアプリやシェアサイクルアプリと行政アプリが連携できれば、ユーザー体験の向上とともに、行政にとっても開発コスト削減につながります。
例えば、行政アプリから「民間アプリへのシームレスな遷移」や、行政が持つ「自転車関連情報(工事情報、イベント情報など)の民間アプリへの提供」などが考えられます。
おわりに
行政アプリに自転車の仕組みが十分に組み込まれていない現状は、自転車業界にとって課題であると同時に、大きなビジネスチャンスでもあります。
環境意識の高まりや健康志向の強まりを背景に、自転車利用促進は社会的ニーズとしても高まっています。
自転車業界が単なる「モノ売り」から脱却し、デジタル時代における都市モビリティの重要なステークホルダーとして行政とのパートナーシップを構築することで、業界全体の社会的地位向上とビジネス拡大につながるでしょう。
行政アプリという「公共のデジタルインフラ」に自転車文化を根付かせるために、業界が果たすべき役割は大きいのです